赤ちゃんが産まれるとお宮参りやハーフバースデイなど沢山のお祝い事があります。
赤ちゃんのお世話は忙しく、成長はあっという間で行事まで手が回らない事がありますよね…。
成長を見守る中「お食い初めはいつするのか」焦って調べた経験はありませんか?
お食い初めは生後100日後を目安に行う行事です。
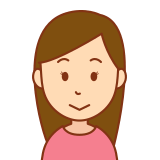
生後100日の数え方が難しいわよね。
そこで、お食い初めの計算方法をご紹介します!歴史についても併せてご説明しますね♪
生後100日の計算方法を知っておけばすぐに確認する事ができるので、お食い初めがいつなのか悩んだ時はとても便利ですよ!
これを読めば安心してお食い初めを準備することができますので、最後まで読んでください!
お食い初めはいつするもの?
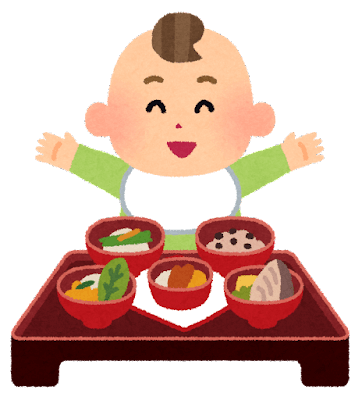
お食い初めは百日祝い(ももかいわい)の中で行う、生後初めて赤ちゃんに食事を食べさせる真似をする儀式のことを指します。
お食い初めはこの百日祝いの中で行う儀式なので、生後100日を目安に行います。
百日祝いは、赤ちゃんが生後100日まで元気に育ってくれた喜びと、今後も健康に成長して欲しいという願いが込められたお祝いです。

お食い初めと百日祝いって呼び方の違いだけかと思っていたけど、それぞれ意味が違っていたのですね!
ただし、地域によってはお食い初めと百日祝いを同じ意味として扱っている所もありますし、一般的には同じ意味と捉えても問題ないようです。
私は恥ずかしながら、子供が生まれるまで百日祝いという言葉を知らず母に促されて初めて知りました…。
また、乳歯が生え始めるのも生後100日ごろなので、食べるものに困らないようにという願いの意味でも生後100日が目安になっています。
あなたがもしお食い初めをいつしたら良いか悩んでいたら、生後100日前後で考えましょう。
生後100日を過ぎてしまったらしない方がいいの?
赤ちゃんや他の子のお世話で毎日慌ただしい日が続くと、どうしてもお祝い行事を忘れがちになります。
私も、下の子のお食い初めをうっかり忘れそうになってバタバタ準備した経験がありました。

お食い初めをいつするかは分かったけど、100日を過ぎていたらしない方がいいの?
生後100日過ぎてお食い初めのことを思い出してしまった場合、どうしたら良いのでしょう?
安心してください!お食い初めは100日過ぎて行っても大丈夫です!
お食い初めは生後100日を目安に生後120日ごろまでに執り行うことが一般的です。
関西の一部の地域ではお食い初めを生後120日目に行う「食い延ばし」という儀式があります。
先延ばしにすることで、赤ちゃんが長生きできるようにと長寿を願う風習があるぐらいなので、100日を過ぎても特に気にし過ぎる必要はありません。
120日目を過ぎても特に問題はなさそうなので、お食い初めをいつするか迷っているならママや赤ちゃんの体調や、家族にあったタイミングに合わせて良い日を選びましょう。
地域によるお食い初めの違いは?
関西の食い延ばしの紹介をしましたが、お食い初めは地域によってやり方が違ってくることは知っていましたか?
関東では赤飯、吸い物、赤飯、魚、赤飯、吸い物の順番で三回繰り返して食べさせる真似をします。
またお食い初めで使用する歯固めの石はお宮参りの神社でもらい、その後お返しするのが決まりになっています。
北海道では、お祝膳のお赤飯に小豆ではなく甘納豆を入れて炊く文化がありますし、大阪では多幸な人生になるよう、歯固めの代わりにタコを使います。
九州博多では漆塗りの器ではなく、白木を曲げて底をつけた博多曲物と言われる器を使用するようでした。
他にも、地域によって「100日祝い」、「食べ初め」、「歯固め」などお食い初めの呼ばれ方が変わります。
地域によって様々な違いがあるので、自分の地域はどんな方法なのか調べてみると安心できるかもしれませんね!
お食い初めをいつにするか計算方法は?
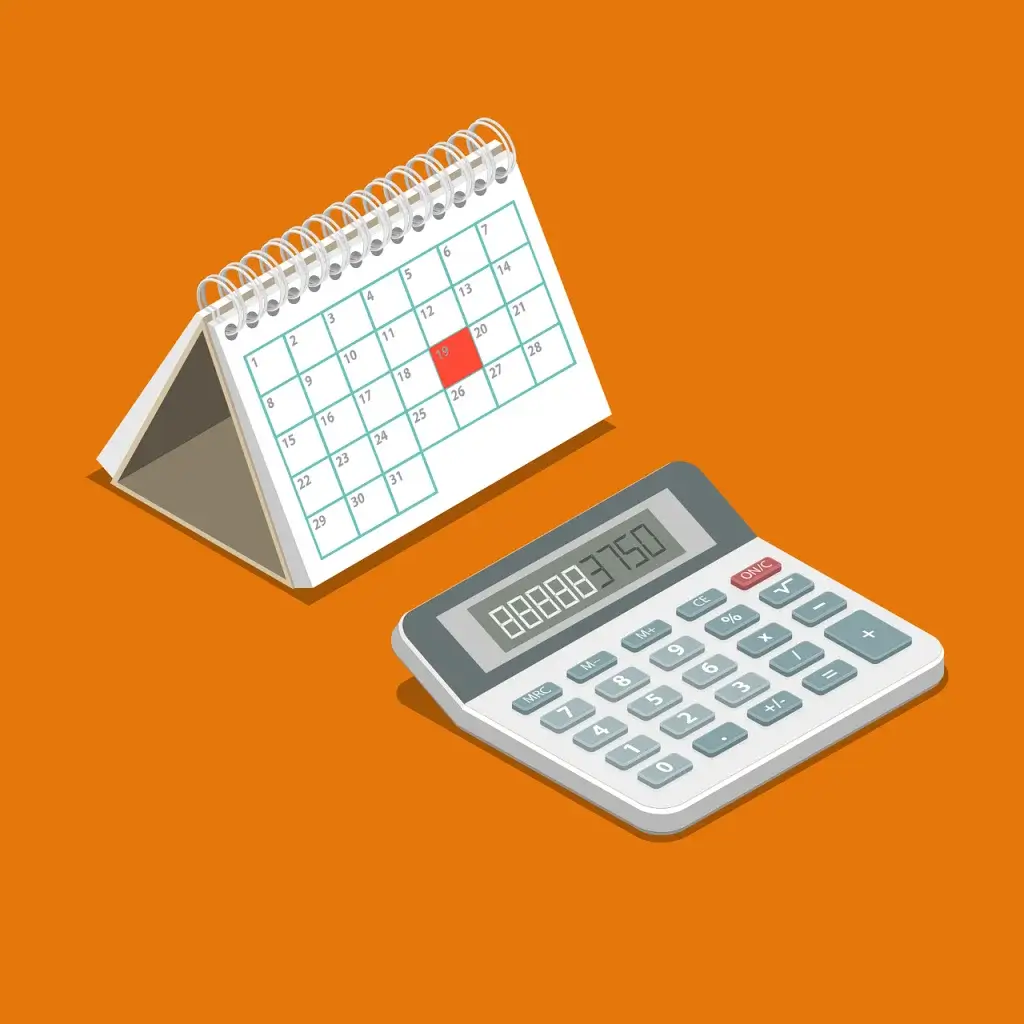
お食い初めは100日前後で行うことが分かったかと思いますが、そうなると次のような疑問が生まれます。

お食い初めをいつにするか決めたいけど、100日の計算方法はどうやってするの?

100日目って、生まれた日を0日として数えていいの?
お食い初めがいつになるか計算方法を考えた時、生まれた日を0日とするか1日とするかで100日目の計算が変わってきますよね。
日本古来の数え方の場合、お食い初めを100日目に行うならば、生まれた日を1日目とし、そこから順に100日目までを数えて計算します。
なぜなら日本では昔から赤ちゃんに関連する伝統行事は生まれた日を1日目と数えるのが一般的だからです。
その為1月1日生まれでその年がうるう年以外だった場合、お食い初めの日程は1月1日から99日後の4月10日を基準に考えます。
それでもお食い初めをいつにするか計算方法で悩まれたら、ネット上には生まれた日を入力するだけで計算してくれるサイトがたくさんあるので利用してみてくださいね。
お食い初めはいつから始まった?
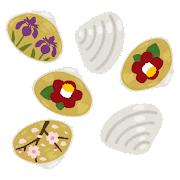
現在の日本では赤ちゃんのお祝いとして当たり前のように行っているお食い初めですが、いつから始まったのでしょう?
私は勝手に江戸時代くらいかなと予想していましたが、実は平安時代というかなり昔に始まった風習でした!
平安時代にあった「百日(ももか)」という行事の中で赤ちゃんにお餅を食べさせていたようで、これがお食い初めの始まりといわれています。

え?!昔の人は赤ちゃんにお餅を食べさせていたの!?
大丈夫!?と心配になりますが、食べさせていたというより、赤ちゃんの口に少しだけ含ませていたようです。
お食い初めの始まりは生後100日ではなく、50日目に行われていたのでその当時は「五十日(いのか)の祝い」といわれています。
重湯の中に五十日餅(いのかもち)と呼ばれる餅を入れ、赤ちゃんの口に少しだけ含ませてお祝いしていました。
時が過ぎ、50日だった日数が100日となり鎌倉時代では餅から魚肉へと変わり「真魚(まな)初め」と呼ばれるようになります。
江戸時代になると、現在行われているようなお祝膳を準備して食べる真似をさせるのが一般的になったといわれています。
いつから始まった行事なのか気になっていましたが、まさか平安時代というのはかなり驚きました!
現代とは違い医療が発達していない時代は、赤ちゃんが無事に育つことが難しかったので、赤ちゃんの成長を祈る儀式やお祝いが様々なタイミングで行われてきました。
いつの時代も我が子に健やかに育って欲しいという願いは変わらないものですね。
豆知識として、お食い初めはいつから始まったのか覚えておくと楽しい話題になるかもしれませんね♪
まとめ

- お食い初めは百日祝いの中で行う儀式なので、生後100日を目安に行う
- 地域によってはお食い初めと百日祝いを同じ意味として扱っている所もあるので、同じ意味と捉えても問題ない
- お食い初めは100日を過ぎて行っても特に問題ない
- お食い初めは地域によってやり方が違ってくる
- 地域によって「100日祝い」「食べ初め」「歯固め」などお食い初めの呼び方が変わる
- 日本古来の数え方だとお食い初めを100日目に行うならば、生まれた日を1日目とし、そこから順に100日目までを数えて計算する
- お食い初めは平安時代からあったお祝い行事
- 最初は生後100日ではなく、50日目に行われていたのでその当時は「五十日(いのか)の祝い」といわれていた
以上、お食い初めをいつするかの疑問に対する紹介記事でした!
お食い初めをやった記憶は赤ちゃんには残らなくても、お子さんが大きくなって写真を見た時に改めて家族の想いを感じることができますよね。
また、赤ちゃんの成長はあっという間ですが、お祝い行事ごとにすくすくと育ってくれた喜びを感じることができるでしょう。
どんな形であれ我が子の成長を思っておこなう行事なので、やってよかったと思えるはずです。
お食い初めを検討されている方は、家族の思い出にぜひともやってみてください!




コメント